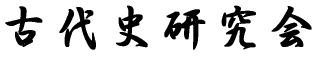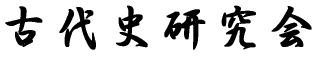|
ポリュビオス『歴史』序文訳註
藤井 崇(京都大学)
ギリシア人歴史家ポリュビオスは、前200年ころペロポンネソス半島の都市メガロポリスに生まれ、前2世紀末にその生涯を閉じるまでに『歴史』全40巻を著した。ポリュビオスの目的は、イタリア半島の一都市であったローマがいかにして地中海世界をみずからの支配下におさめるに至ったかを叙述するというものであり、『歴史』はローマ共和政期、ひいては広くヘレニズム期の重要な歴史史料となっている。
筆者は先に「ポリュビオスとローマ共和政 −『歴史』からみた共和政中期のローマ国政−」(『史林』86-6、2003年、1-35頁)を発表しており、これまで『歴史』におけるローマ共和政に注目しながらポリュビオスに接してきたが、ポリュビオスの『歴史』そのものにたいする自身の関心が高まってきたため、ホームページの場をかりて、『歴史』理解において重要になるであろう序文の訳註をおこなうことにした。この序文は、第1巻の1章から5章を占めており、さらに細かくみると、1章1節から3章6節までは、『歴史』全体の主題や歴史叙述の効用が説かれ、3章7節から5章5節では、特に第1巻と第2巻にたいする導入がなされている。この『歴史』序文訳註は、ホームページ上にて数次にわたってなされるが、今回は序文前半部、すなわち第1巻1章冒頭から3章6節までの翻訳を掲載する。
底本は、Th. Buettner-Wobst 編のトイプナー版である。適宜、ローブ版、ビュデ版、アルテミス版の各国語訳を参照した。また、F.
W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, 3 vols., Oxford, 1957-1979 は、やはり非常に有用である。さらに、現在も作業進行中であるポリュビオス語彙辞典(A.
Mauersberger und Ch.-F. Collatz et al. (hrsg.), Polybios-Lexikon, Berlin, 1956-)も参考にした。
なお、訳文中の[ ]は、原文にはないが意味を明確にするために筆者が補った語句であることを示す。
第1巻
1章
私たち以前に歴史を書いた者たちによって、もし歴史自体を称賛することが無視されたならば、過去の事柄に関する知識以上に頼りになる教育を人間は持ち合わせていないのだから、このような歴史を選び受け入れるように、おそらく私は皆を説得しなければならなかっただろう。しかしながら、少数でも簡単でもなく、よくいわれているように、すべての歴史家が歴史から学ぶことは政治の仕事にたいする最高に信頼のおける教育・訓練であり、他人の[運命の]変転を思いおこすことはテュケーの浮沈を高潔に耐えることを可能にするもっとも明確な唯一の教師であるといって、先に述べたことを肝心要のものとして扱っていた。そのため、丁寧にかつ多くの者によっていわれたことについて同じことを語るのは、誰にとっても、少なくとも私にとっては明らかに適当とは思われない。私が叙述することを選んだ出来事のまさにこの意外性[だけ]で、老いも若きもすべての人々にたいしてこの書物を読むように訴え、せき立てるには充分だからである。なぜならば、どのようにして、そしていかなる政体によって、53年にも満たない期間でほとんどすべての「世界」が征服され、ローマ人による唯一の支配のもとに入ったかを知ろうと望まないほど無思慮で、怠惰な人間が果たして存在するのだろうか[ということである]。これは、以前に生起したとは認められないことである。さらに、この知識を得ることよりも他のことをより有益と考えて、その他の事柄の観察や学習に熱心になる者が、果たしているのだろうか。
2章
私たちのテーマについての研究が、いかに予想を超え、大きなものであるかは、著述家が非常に詳しく叙述をおこなってきた以前の国家のうちで最も有名なものをローマ人の卓越さと比較対照するならば、きわめて明確になるだろう。比較対照の価値のある国家は、次のものである。ペルシア人は、一定期間巨大な支配と権力を保持した。しかしながら、彼らはしばしばアシアの境を大胆にも踏み越えたので、支配権のみならず自身にたいしても危険を冒すこととなった。ラケダイモン人は、長い間ギリシア人の支配権をめぐって争ったが、ついに勝利をおさめると、それをかろうじて12年間は安定的に保持した。マケドニア人は、ヨーロッパをアドリア海の地域からドナウ河まで支配したが、これは先に述べた土地[ヨーロッパ]の中でまったく重要性の低い部分のように思えるだろう。その後、彼らはペルシア人の支配を打ち砕いた後に、アシアの支配権を奪取した。しかし、彼らはもっとも多くの土地と国家を支配していたと考えられたにもかかわらず、「世界」の多くの地域を支配できぬまま残していたのである。というのも、マケドニア人はシチリアもサルディニアもアフリカも[その支配権を]ちっとも争おうとはせず、また率直にいってしまうと、ヨーロッパの西方の諸民族のうちもっとも好戦的な種族を、彼らは知らなかったからである。ローマ人こそは、部分的にではなくほとんどすべての「世界」を服属させて、自らの権力の優越を、同時代の者たちには打ち勝ちがたいものとして、また後世の者たちにとっても凌ぎがたいものとして残したのである。彼らが何に基づいて「世界」を保持したかについては、叙述からより明確に把握することができるだろう。また、実際的歴史という方法が、学を好む者たちにどれほど大きな、どれほど偉大な貢献を為すものなのかについても、同様に叙述からより明らかとなろう。
3章(6節まで)
私たちの叙述は、第140オリンピア期からはじまるであろう。[当時の]出来事のうち、ギリシア人のところでは同盟市戦争とよばれる戦争があり、それはデメトリオスの子、ペルセウスの父であるフィリッポスが、アイトリア人にたいしてアカイア人と組んで[自身の]最初の戦争としておこなったものである。また、アシアに居住する者たちのところでは、コイレ・シリアをめぐる戦争があり、これはアンティオコスとプトレマイオス・フィロパトルが互いに争った戦争である。さらにイタリアやアフリカでは、ローマ人とカルタゴ人に戦争が生じ、多くの者はこれをハンニバル戦争とよんでいる。これらは、シュキオンのアラトスによる叙述の末尾に継続される。これら以前の時代においては、物事のはじまりやおわり、同じく場所の点でも、それぞれの行為がてんでばらばらであったために、「世界」の出来事には何ら統一がないかのごとくであったのである。しかし、これらの時代以降、まるで歴史は統一体となり、イタリアとアフリカの出来事がアシアやギリシアのそれと紡ぎ合わされ、万事の方向がひとつの完成へと向かったかのようであった。それゆえに、彼らについての歴史叙述のはじまりも、まさにこの時にしたのだ。というのも、先述の戦いでローマ人はカルタゴ人を打ち負かし、「世界」支配に向けて非常に重要で大きなことをやりとげたと考えたので、こうして彼らはこの時はじめて残りの地域に手を伸ばし、軍隊を引き連れてギリシアとアシアの地に進攻しようと決心したからである。
|