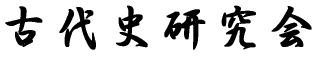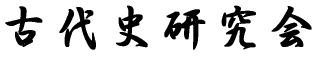○第2回古代史研究会大会 発表要旨
研究報告1 比佐 篤(関西大学)
中期共和政ローマの政治社会における勝利の意味
前3世紀初めにイタリア半島を征服したローマは、カルタゴとの戦争をきっかけにイタリア半島外部でも次々と戦争を実行する。その多くに勝利することで、共和政末期には地中海世界において最大の覇権を握ることになる。
戦争が恒常的に行われていたのであれば、勝敗の結果そのものとは別に、鮮烈に加わった者たちや社会へも大きな影響を与えたことは想像に難くない。戦争終結後に外部から莫大な富や奴隷などが流入したことからも、このことはうかがえる。そして、それはローマに勝利をもたらした指揮官たちにおいても同様であり、戦争での勝利によって戦利品の獲得や市民の間での人望を得ることも可能であった。指揮官が高位の公職者であったことを踏まえれば、戦争での勝利はローマの政治にも関連すると考えられ、こうした人物に対する個別研究からローマの政治史を考察する研究が盛んに行われてきた。しかしながら、個々の人物とそれに関する事例を検証しただけでは、それぞれの状況における戦争と政治の関係性が、共和政ローマ史全体を通じて共通の事例であるのか、それとも特殊な事例にすぎないのかを捉えることは出来ない。
そこで本発表では、イタリア半島外部へ進出する第一次ポエニ戦争期から、対外戦争が政治家同士の政争と大きく関わる共和政末期の直前までを対象とし、戦争での勝利が共和政ローマの政治家や政界においていかなる意味を持っていたのかについて、通じてきな考察を行う。これによって、制度的にも政界内部でも大きな変動は生じなかったとされる中期共和政ローマにおいて、戦争での勝利の意義が微妙に変化し続けていたことを明らかにしたい。また、近年の共和政ローマ史研究においては、その政体を巡る議論が活発に行われている。本発表では、こうした議論に対して新たな見解を提示することも試みたい。
研究報告2 庄子 大亮(京都大学)
古代ギリシア人にとっての過去 'ta archaia' ―「神話」をめぐる一考察―
現代において「神話」というとき、それは科学や歴史に相対するもの、というイメージをもっている。神話mythという言葉は古代ギリシアの「ミュートスmuthos」(神話や物語と訳される)に由来するが、古代ギリシア人は現代と同じ「神話」概念はもっていなかった。我々からすれば「神話」に思える物語は、古代ギリシアにとっていかなる意味を有していたのであろうか。本報告では、ギリシア人の「神話」的な過去‘ta
archaia’‘ta palaia’のとらえ方に焦点をあて、ギリシア人の心性についての理解を深めたいと考える。
まずは、古典期アテナイの伝説をもとに、ギリシア人にとっての遙かな過去の意味を探っていく。無文字の暗黒時代を経て新しい社会、すなわちポリスを成立させたギリシア人は、遺物や口承の記憶をもとに自分たちの偉大な過去(我々がミュケナイ時代として把握する時代)を再構成した。つまりそれは彼らなりに構成された事実であったわけである。さらにギリシア人は、暗黒時代を挟んで断続の意識を持っていたがゆえに、偉大な過去とのつながりを強く求めた。それは過去の客体化に結実し、単に非合理的思考としては理解することのできない、様々な意味をもって伝説が語られたのであった。こうした過去のとらえ方をより鮮明に浮き彫りにするものとして、プラトンが『ティマイオス』、『クリティアス』において語るアトランティス物語についても検討する。
本報告は、「神話」の考察を通じ、近現代の思考のあり方を照らし出したいという試みの出発点でもある。最後に展望・補論として、近代における「神話」概念と、科学の興隆、進化論の影響、ヨーロッパのオリエンタリズムなどとの関わりについてもふれたい。
研究報告3 中井 義明(同志社大学)
hos epi to poly ―文字史料と碑文史料の狭間―
デロス同盟の貢税についてはトゥキュディデスをはじめとする文献史料とメリットやマクレガーらが編集した『アテナイ貢税表』に代表される碑文資料との間に大きな齟齬が生じていることは既に多くの研究者によって指摘されている。文献史料が同盟発足時の460タラントンから出発し、ペロポネソス戦争勃発時の600タラントン、ペリクレス死後の1300タラントンと右肩上がりの増額の過程を想定させるのに対して、碑文資料は前454/3年度の400タラントン代という低い水準で低迷している。この数字上の乖離は同盟国に対するアテナイの支配強化をどのように評価するのか、という問題とも関連しているので重要である。
研究史的にはトゥキュディデスを初めとする文献史料に問題があるというアトキンソン、碑文はアテナイの貢税収入の総額を記録していないと主張するゴム、査定と歳入との間には差額が生じて当然とするカレット―マークス、そして査定の減額を想定するメクズ、らの学説に分けることができる。
本発表者自身「アリステイデスの査定」と前454/3年度の貢税初穂料の乖離を査定総額の減額を想定することによって解決しようと試みた。しかし、重要な問題が残されている。それはペロポネソス戦争勃発時になると文献と碑文との乖離はさらにひろがってしまうという事実である。
本発表では、問題がペリクレスの演説に使われているhos epi to poly(Thuc.II.13.3)の解釈にあり、「平均して」と訳すことによって乖離が生じてしまったと論じる。
研究報告4 藤井 慎太郎(同志社大学)
ローマ属州支配とバタウィ族の乱
紀元69年、ガリア北東部でゲルマン族のバタウィ族を中心とした反乱が生じた。いわゆるバタウィ族の欄と呼ばれるこの反乱は、ライン川流域一体に居住する諸部族に拡大し、ついにはライン川流域に駐留していたローマ軍を降伏させるに至った。反乱自体はウェスパシアヌス帝の派遣したローマ軍により鎮圧されたが、ローマ帝国領域外に居住するゲルマン人も参加しており、対応を一つ誤れば、帝国の安全保障に重大な支障を与えかねないものであったのである。
このバタウィ族の乱に関して、多くの先行研究が存在しているが、その研究の大部分は、反乱を起こした首謀者であるユリウス・キウィリスの反乱動機に関心が集中している。この反乱を伝えるほとんど唯一の史料であるタキトゥスの『ヒストリアエ』であるが、そのなかの反乱原因についての説明を信頼せず、反乱を当時ローマ帝国全土に及んでいた内乱の一環として捉え、キウィリスが帝国内の党派対立のなかでウェスパシアヌス派に与していたとする見解とこれに対する反論である。反乱動機に関する研究はこれまでかなり行われているが、どちらの側の考察においても反乱の一側面のみを強調してこの反乱の性格を規定しようとしてきたように思われる。
そこで本報告では、先行研究を踏まえつつ、反乱原因の解明に終始するのではなく、バタウィ族の乱への参加者の分析を通じて、この反乱の全体像について検討する。さらにこの反乱がローマ支配の実態を考察する上でどのような意義を持っているのかについても検討していきたい。
研究報告5 豊田 浩志(上智大学)
サンチャゴ巡礼における史実と伝承 ―使徒ヤコブの墓所をめぐってー
地中海キリスト教世界では、古くから三大巡礼地としてエルサレム、ローマ、サンチャゴが著名である。発表者は文部科学省科研基盤研究(B)「環地中海世界の聖地巡礼と民衆信仰」(研究代表者:流通経済大学社会学部教授関哲行)に参加したこともあって、サバティカル・リーヴを利用して本年4月からローマに居住、夏には、パレスティナ巡礼の聖遺物コレクションで有名なミラノ近郊のMonzaを発して、フランスの巡礼地Saint-Maximin-la-Ste.Baume、Arles、Saintes-Maries-de-la-Mer、それにLourdesを訪問、Saint-Jean-Pied-de-Portに至り、そこから徒歩でのSantiago de Compostela巡礼を試み、全行程774キロのうちLeonまでの463キロを20日間で踏破、その後バスでサンチャゴに向かい、大西洋岸のさい果ての地Fisterra(=Finis terrae)も訪れることができた。聖ヤコブ年にあたる来年夏、改めて後半300キロに挑戦予定である。
ところで、なにがしかの史実と確固たる聖地としての背景を持つエルサレムやローマと異なり、サンチャゴには明確な歴史的宗教的前史がない。しかるに、巡礼者は11世紀以降増加、12・3世紀には年間50万人に達したといわれている。この人気の秘密は何か。聖地サンチャゴに関してどのような物語が編まれ、そしてそれがなぜ民衆を巡礼へと突き動かしたのか。本報告では、とりわけ使徒ヤコブの墓所をめぐっての集団的イメージの創生プロセスと、1946年以来のサンチャゴ大聖堂祭壇下の発掘作業の成果を交差再検討することによって、サンチャゴが担った他の二大聖地の補完機能としての役割について論じてみたい。
(所属などは発表時のものです。) |
Copyright © 2004 The Society for the Study of Ancient History. All rights
reserved
|