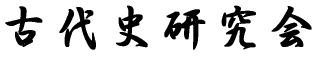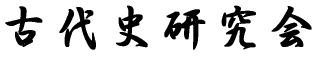○第7回古代史研究会大会 報告要旨
「ローマのような都市」レプキス・マグナの形成
青木 真兵(関西大学大学院)
レプキス・マグナは現在のリビア西部に位置し、地中海に面する都市であった。もともとは前7世紀にフェニキア人によってつくられ、やがてローマの属州下に入る。後109年に植民市coloniaの地位を与えられ、後203年にはレプキス出身の皇帝セプティミウス・セウェルスによってイタリアの町と同様に税金が免除される。こうして属州アフリカの首都カルタゴに次ぐ第二の都市として繁栄を迎え、「ローマのような」大理石に彩られた壮麗な都市へと変貌したのである。
現在のレプキス・マグナ研究は、主にポスト帝国主義的なローマ化理解のもとに行われる。つまりローマ帝国という文明世界への参加を帝国下の人びとが望み、ローマが文明を与えたというかつてのような帝国主義的理解を否定する。その上で文化を相対化し、ローマ文化と現地の文化が出合ったことによる双方向からの「文化変容」としてのみローマ化を捉えるのである。そしてこのような文化理解は、都市エリートが自らのステータスシンボルとしてローマを利用したという「自己ローマ化」と結びつき、彼らが自主的に「ローマ」を求めたことが強調される。しかし文明化としてのローマ化が否定されてしまうとローマ化という概念自体が曖昧になってしまい、では「ローマ」とはなんだったのか、という問いが提示されることになる。
このような経緯から、ローマ化という文化変容が起こった原因として「ローマによる支配」の存在に立ち返るべき、という見解もみられる。つまりローマと現地の文化はローマによる支配なくしては出合うことはなかったのであり、その「支配」という事実が文化変容を引き起こしたとする。だが、このとき言及される「ローマによる支配」がイタリアからの人びとの移住や軍事的行動を伴うものであり、ローマ支配の中心地が主に考察の対象となっている。一方、レプキス・マグナはローマによるアフリカ支配の周縁部であり、ローマの直接の軍事的支配が及ばなかった地域である。そのため「ローマによる支配」という見解ではその様相を十分に捉えきることができない。
以上の観点から「自己ローマ化」理解によって語られる都市レプキス・マグナを、属州アフリカへの「ローマ支配」という文脈のなかでどのように位置づけるかについて考察する。
宦官エウトロピウスの行政改革
南雲 泰輔(京都大学大学院・日本学術振興会特別研究員DC)
宦官のエウトロピウスがローマ帝国東部宮廷で公的経歴を開始するのは、テオドシウス1世の治世、おそらく393年ごろと推測されている。当時の帝国東部宮廷の実力者は、オリエンス道長官(praefectus
praetorio Orientis)として皇帝に次ぐ地位にあった官僚ルフィヌスで、彼とエウトロピウスとは敵対関係にあった。ルフィヌスは395年に殺害されてしまうが、これは帝国西部の武官スティリコと結んだエウトロピウスの陰謀であったらしい。
ルフィヌス失脚後の帝国東部宮廷の状況は、史家によって「エウトロピウス体制(the
régime of Eutropius)」と呼ばれた。エウトロピウスは、395年に宮内長官(praepositus
sacri cubiculi)に就任、398年にパトリキウスとなり、399年にはコンスルに就任する。このエウトロピウスのコンスル就任は、宦官のコンスル就任としてローマ帝国史上初の事例であり、395年から399年まで、約4年間にわたって帝国東部宮廷の事実上の最高権力者として、エウトロピウスが有した権力の大きさを物語っていよう。
この宦官エウトロピウスは、学説史上において、第一には宦官研究の立場から、第二には文学研究の立場から、各々論じられてきた。しかし、前者にあってエウトロピウスは、ビザンツ帝国期を通じて遍く存在した宦官の先駆かつ典型例として類型的に理解されたのであり、また後者にあっては、帝国西部の詩人クラウディウス・クラウディアヌスに関する研究の一環として取り上げられたのであって、ともに貴重な示唆に富む研究でありながら、政治史的・行政史的な問題意識に発したものではなかった。そのため、これらの研究においては、宦官エウトロピウスの行なった政策が具体的な考察対象とされたこともなかったのである。
そこで本報告では、宦官エウトロピウスの行なった行政改革を取り上げ、その後期ローマ帝国史上の政治史的・行政史的位置づけを探るべく、検討を試みたい。
ローマ期エジプトにおける地方名望家の活動
―2世紀アルシノイテス州のパトロン家の事例から―
高橋 亮介(日本学術振興会特別研究員PD)
プトレマイオス朝の滅亡とともにローマ帝国に組み込まれたエジプトを、ローマ属州として特徴づけたものが、都市公職(archai, honores)と公共奉仕(lituregiai, munera)による地方行政機構の構築であり、また、それを担う都市富裕層の創出であったことは、パピルス史料を扱う研究者によって認められて久しい。このエジプトにおける都市富裕層=名望家は、帝国他地域における都市参事会階層に比するとされ、現代の研究者によって「ギュムナシオンの階層」と呼ばれている。本報告は、史料に恵まれた地方名望家の一家族の例に、地方名望家の活動を再構成しようとするものである。
本報告では、まず「ギュムナシオンの階層」について研究者によって諒解されている基本的事項と最新の研究動向を紹介した後に、彼らの活動を具体的に活写するべく、2世紀アルシノイテス州(現在のファイユーム地方)の地方名望家であったパトロンの子孫たちの活動を考察する。
パトロン家については、ファイユームの南端に位置したテプテュニス村の遺構から発見されたパピルス文書を中心に120点あまりの史料から知られる。彼らに関する史料は同村周辺での所領経営に関するものが多いが、それでも地方名望家の様々な役割と活動を一家族の中に見て取ることができる。彼らは都市公職を務め、地方行政のための公共奉仕を務めた。また私人として裁判に関わり、所領を直接・間接的に経営し、金品の貸付などの経済活動を行っていた。さらに彼らの活動は、アルシノイテス州にとどまることなく、アレクサンドリアとの関わりを有してもいた。
なるほど、史料から知られる彼らの活動は、ローマ帝国における地方名望家像を刷新するほどの新しさに満ちたものではないだろう。しかし、日々の生活を記録したパピルス文書から、碑文史料や法文史料からは知り難い、生き生きとした地方名望家の姿を具体的に描くことができるのではないだろうか。
Tabulae Caeritum考 ―ケーンソルの譴責と古代ローマの市民権―
毛利 晶(神戸大学文学部教授)
紀元後2世紀のローマの文人アウルス・ゲッリウス(Gell. N.A. XVI, 13, 7)によると、「カエレ人の表(Tabulae Caerites)」と呼ばれるものが存在し、そこにはケーンソルから譴責のために(notae causa)投票権を剥奪された市民の名が記されていた。名称の由来は、ガッリア人戦争(所謂ワッローの紀年法によると前390年)の時にカエレ人がローマの神器を引き受けて保管したので、これに感謝したローマ人が彼らに義務と負担は免除してローマ市民権の栄誉のみを享受することを認めたことにあり、譴責を受けた人々が登録された表を「カエレ人の表」と呼ぶのは、意味の逆転だという。地理学者ストラボーも『地誌』の第5巻でカエレ人がガッリア人戦争時にローマ人に対して示した好意を述べたあと、同様の証言を行っている(Strabo V,2,3)。
この「カエレ人の表」について、近代におけるローマ史研究の基礎を築いたドイツの歴史学者Th. Mommsenは以下のように考えた。もともとこれは、ローマに従属することになった共同体の構成員(彼らはローマの民会での投票権がなく、Mommsenは「半市民」と呼ぶ)の表で、完全なローマ市民だがローマ領に土地を所有しない者もこの表に名前が記された。しかし前312年にケーンソル職に就いたアッピウス・クラウディウス・カエクスは土地を所有しない市民もトリブスに配属し、その結果全ての完全市民がケーンソルによって所属トリブスを決められるようになる。その後、前304年にクイーントゥス・ファビウス・マクシムスとプーブリウス・デキウス・ムスがアッピウス以前の制度の復活を目指したが、この試みも完全市民は全てトリブスに登録するというアッピウスの改革の原則を崩すものではなかった。こうした理解のもとMommsenは、ケーンソルが譴責を行った完全市民の名を完全な意味で「カエレ人の表」に記入したのは、土地を持たない完全市民と半市民がトリブスから排除されていた時代に限られ、アッピウスの改革以降は、ケーンソルが行う処罰は所属トリブスの変更に限られただろうと推測する。こうしたMommsenの理解は様々な問題を含むが、考察の範囲をケーンソルの譴責とローマ市民権の問題に限った場合でも、次の二点が検討課題となる。一つは「カエレ人の表」とcives sine suffragio(投票権を持たないローマ市民)の関係で、この表はもともと政治的な権利を持たない半市民の名簿だったと捉えるMommsenの理解は正しいかという点。二つめは、この表とケーンソルから譴責を受けた市民との関係で、そこには、ケーンソルの譴責を受けた者が被ったと伝えられるtribu mouereという措置の内容に関する問題と、ケーンソルが譴責を行った市民のリストが何故「カエレ人の表」と呼ばれたのかという問が含まれる。報告ではこれらの点について先行研究を整理した上で若干の考察を加え、ローマ共和政期におけるローマ市民権の理解を深めることを目差す。
(所属などは発表時のものです。) |
Copyright © 2004 The Society for the Study of Ancient History. All rights
reserved
|