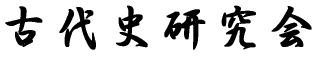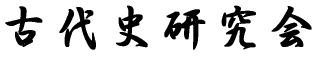○第10回古代史研究会大会 報告要旨
プトレマイオス朝エジプト在地社会における紛争解決
石田 真衣(大阪大学)
強力な中央集権的専制国家であるというプトレマイオス朝エジプトの国家像が見直されるようになってから久しい。しかしながら、法と秩序の問題については、いまだ制度史に偏りがちであり、在地社会の実態に迫る議論は十分になされていない。本報告では、ファイユーム地方とテーベ地方の事例を中心に取り上げ、在地社会における秩序維持のあり方を明らかにしたい。
主な考察対象は、私的な紛争の解決を地方役人に求めるギリシア語嘆願書である。史料としての嘆願書は、これまでの同王朝史研究における諸分野で断片的に扱われてきたが、嘆願システムそのものを対象とする研究はなされてこなかった。ここでは、個人が自発的におこなう嘆願書の提出から、地方役人による受領と対応までの過程を分析し、嘆願者と地方役人の両方の視点から、紛争解決の一手段としての嘆願システムを位置づける。
一方で、これらギリシア語嘆願書の出土は、この時代ギリシア・マケドニア人が多く居住するファイユーム地方に多くみられる。同王朝の伝統的な国家像は、ファイユーム地方からのギリシア語パピルス文書の分析に偏った結果であり、近年の諸研究では、この時代以前からの伝統を色濃く残すテーベ地方との地域差を意識する傾向にある。そこで、第二の考察対象として、テーベ地方から出土するデモティック(エジプト語)神殿宣誓史料を取り上げる。この史料は、地方神殿において雪冤宣誓のかたちで和解を成立させる紛争解決の一手段を示す証拠である。先行研究において、この時代のエジプトにおける秩序維持システムの枠組みのなかで捉えられてこなかったこの伝統的な和解システムの考察は、同王朝の支配体制を問いなおすことにもつながる。
以上の考察対象を比較検討しながら、それぞれの地域における紛争解決システムの特質を明らかにし、さらに、プトレマイオス朝国家の社会統制のあり方についても言及したい。
ヘレニズム諸王国とローマの衝突
――アンティゴノス朝・セレウコス朝とローマの戦争を中心に――
柴田 広志(京都府立大学)
ヘレニズム諸王国とローマは、前215年以降、数度にわたり戦火を交えた。このうち、アンティゴノス朝のピリッポス5世、およびセレウコス朝のアンティオコス3世とローマとの戦争は、その後の地中海世界の覇者を決定するものであった。両王との戦役に勝利したローマは、以降、地中海の覇者として君臨していくこととなった。
さて、ローマが覇者となったということは、とりもなおさず、ローマという「余所者」がヘレニズム世界に君臨するに至ったということを意味する。ここで注意したいことは、前270年代のガラティア人の侵入以降、ヘレニズム諸王国は「蛮族」として位置づけた外敵を撃退することによって、王権の正当性を確保してきたということである。したがって、ローマという「他者」に対する敗北と屈服は、これらの諸王国の王権に大きな影響を及ぼしたものと想定しうる。ヘレニズム諸王国は、この新参者であるローマの進出という問題に直面したとき、どのように対処していったのだろうか。そして、ローマとの戦争での敗北は、敗者であるヘレニズム諸王国に、如何なる衝撃を与えたのだろうか。
本報告は、ヘレニズム諸国に対するローマの優位を決定づけた、セレウコス朝の「大王」アンティオコス3世とローマの間に戦われた戦争を中心に、この問題を考察する。また、論の関係上、アンティオコス3世より前にローマと戦って敗れた、マケドニアのピリッポス5世についても触れる予定でいる。
コンモドゥス帝期ブリタンニアにおける皇帝擁立
脊戸 里央(京都女子大学)
五賢帝最後の皇帝であるマルクス・アウレリウスの息子コンモドゥスが殺害されたことに端を発した193年の内乱は、セウェルス朝の始祖となるセプティミウス・セウェルスの勝利で幕を閉じる。この内乱において、属州ブリタンニアの総督であったクロディウス・アルビヌスは、セウェルスより副帝(カエサル)に任じられるものの、後に自ら皇帝(アウグストゥス)を名乗り、ブリタンニア駐屯軍を引き連れ、セウェルスとの決戦に臨んでいる。このアルビヌスは、ブリタンニアで「皇帝」となった初の人物として脚光を浴びてきた。
しかしながら、これに先立ちコンモドゥス帝期ブリタンニアではすでに二度、駐屯軍団による皇帝擁立事件が起きていた。後に訪れる「3世紀の危機」のような不安定な状況下でならともかく、帝国全土が比較的安定していたとされるコンモドゥス帝期に、未遂で終わったとはいえ、皇帝擁立の動きがあった事は注目されるべき事態であるが、これまで充分に検討されてこなかった。そこでまず本報告では、この擁立事件の再検討からはじめる。
コンモドゥスが単独統治を開始した180年から、皇帝に代わって帝国統治を担ってきたのは近衛長官であるペレンニスだった。先行研究では、このペレンニスの失脚とブリタンニアの軍団司令官プリスクスの皇帝擁立事件とを結びつけて考察してきた。だが、本報告はその問題点を指摘し、プリスクス擁立を、その後に起きた総督ペルティナクスの擁立事件と関連づけることによって、当時のブリタンニア駐屯軍の置かれていた状況を論じていく。
これらの考察を通じ、ローマ帝国におけるブリタンニアの特異性が、コンモドゥス帝期に表面化したこと、さらに後のアルビヌスの皇帝宣言や、続くセウェルス帝の統治に影響を与えたことを明らかにする。
史料としてのアンミアヌス・マルケリヌス
小坂 俊介(東北大学)
「同時代人の見解が陥る偏見や感情により歪曲されることなく、著者自身の同時代史をもっとも正確かつ誠実な筆をもって伝えてくれている道案内の人物」(ギボン著、中野好夫・朱牟田夏雄訳『ローマ帝国衰亡史』第四巻
ちくま学芸文庫 1996年 278頁)。18世紀の歴史家エドワード・ギボンがこのように賛辞を送った人物が、330年頃にローマ帝国東部に生まれ、4世紀末に没したとされる著作家アンミアヌス・マルケリヌスである。アンミアヌスの著作Res
Gestae『歴史』は本来、皇帝ネルウァからウァレンスまでの時代、すなわち紀元後96年から378年までのおよそ300年間の出来事を記していたと考えられる。現存するのは354年以降を扱った14巻の途中から最終巻である31巻までとはいえ、その部分はアンミアヌスが生きた同時代の様々な出来事を詳細に伝えてくれている。それだけにこの著作は、当時のローマ帝国のみならず地中海世界の歴史を正確に記述したものとして重要視されてきた。20世紀半ばより、アンミアヌス自身の立場や感情に由来する偏見がその記述に表れていることが明らかにされてはいるが、一方で史実の記録は正確であるとみなされてきた。
しかし特に1980年代末ごろから、そうしたアンミアヌスの記述の正確さに疑いの目を向ける研究が現れる。特に1998年に公刊されたT. D. Barnesの研究は、アンミアヌスの著作を「想像が生んだ作品」とみなすべきである、とまで述べている。この問題提起は大きな反響を呼んでいるが、同時に批判も寄せられている。本報告では研究史に特に大きな影響を与えたBarnesとF. Paschoudの研究の意義を検討しつつ、われわれがアンミアヌスの著作を史料として用いる際にはいかなる点に注意すべきか、という問題を考えたい。
また1970年代以降のいわゆる「古代末期」研究の隆盛によって、アンミアヌスの著作に対する関心も高まり研究が増加したことも見過ごせない。こうした研究動向にも目を向けつつ、現時点でのアンミアヌス研究の現状を概観してみたい。
(所属などは発表時のものです。) |
Copyright © 2004 The Society for the Study of Ancient History. All rights
reserved
|