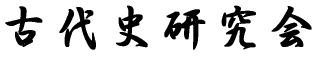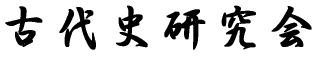○第13回古代史研究会大会
前4世紀中葉以降のアテナイにおける外国人の動向
――亡命者の存在に注目して――
篠原 道法(立命館大学)
前4世紀中葉以降、特にリュクルゴス時代とも呼ばれる30年代初頭から20年代半ばにかけてのアテナイ社会と外国人の関係をめぐっては、同時期の経済・財政状況を踏まえて、交易と関連の深い地域――黒海沿岸や地中海南西岸――出身者との関係の構築が市民によって積極的に試みられていたことや、その結果として実際に彼らが社会に定着していたことがしばしば指摘がされてきた。
その一方で、こうした社会関係には、勿論、アテナイを取り巻く政治情勢も大きな影響を与えていた。特に社会の内部での外国人の動向を把握しようとする際に、亡命者の存在を見過ごすことはできない。前4世紀中葉以降、とりわけマケドニア王国の影響により継大規模かつ継続的に亡命者が出ており、アテナイは対外政策の一環としてしばしば彼らの受け入れを行っていたことが知られている。このような状況が外国人の行動に大きく作用したことは容易に推察される。しかしながら管見の限り、この時期の社会における亡命者の実情――実際にどれほどの亡命者がアテナイに流入し、また彼らはいかに社会と関わったのか――については、これまで十分には考察されてきていない。彼らの存在も加味することで、アテナイ社会における外国人の動向を、より良く理解することができよう。
そこで本報告では、かかる点を踏まえて、外国人関連の碑文――主に彼らが残した墓碑――を手掛かりとして、前4世紀中葉以降における亡命者のアテナイへの流入及び、彼らの社会における活動の実態について検討をする。その際には、同時期の経済情勢を背景としてアテナイに定着したと考えられる外国人の事例との比較も行う。こうした考察を通じて、前4世紀中葉以降のアテナイ社会を理解するための一助としたい。
前5世紀アテナイの艦隊乗組員
――IG.I (3).1032
(IG.II(2).1951)の分析を中心に――
岡田 泰介(高千穂大学)
The Athenian Naval Catalogueと通称される碑文(以下NC)は、前5世紀のアテナイ社会に関する比類のない史料でありながら、全体の四分の一程度が大小11個の断片(最近発見された小断片を除く)として現存しているにすぎない保存状態の悪さと、まさにその比類なさゆえに、歴史的文脈への位置づけが容易でない。そのうえ、1927年までに発見されていた9断片のみを利用したJ.Kirchnerの不完全な復元案(IG.II(2).1951)が、碑石の精査にもとづくD.R.Laingの抜本的な修正案(1965)の発表後も、Laing案に依拠したD.Lewisの新しいテクストが1994年にIG.I(3).1032として現れるまで、NCの標準的なテクストとして広く利用され続けた。そのためか、この史料を正面から論じた研究は少なく、アテナイ海軍史研究に関しては一定の蓄積のある日本の学界においても、ほとんど取りあげられたことがない。
NCは、現存部分で4隻、実際には8隻の三段橈船乗員の名簿である。各船の乗員名は、トリエラルコス以下船上での役割ごとに配列され、漕手はさらに身分(市民・外国人・奴隷)ごとに分類されている。NCの発見当初から注目されたのは、乗員の過半数を非市民が占めており、なかんずくその中で奴隷(therapontes)が少なからぬ割合を占めていることである。それはアテナイ社会の一断面というべく、NCをめぐる議論の焦点はその評価に絞られる。ペロポンネソス戦争末期の危機的状況下における特殊事例との評価が大勢を占めていた研究動向は、近年、アテナイ海軍における奴隷の日常的使用を主張するP.Huntの所説をはじめとして、一般化の方向へと流れを変えつつある。本報告では、そのような研究動向に棹さしつつ、NCの評価に関して幾つかの新視点の提示を試みる。
ギリシアの犠牲式における「持ち出し禁止」について
――近年のオリュンピオス/クトニオス問題を手がかりに――
山内 暁子(佛教大学)
古代ギリシア宗教の中心となる儀礼は、動物犠牲であった。この前提について疑問が呈されることはないが、研究史においては様々な観点が存在する。従来は、人類学的な立場から人間社会の紐帯となる罪意識を読み取るもの、あるいはシュンポシオンまたは「共食」に至る社会史的/政治史的な意義の強調が優位であった。
しかし、近年は動物犠牲を宗教史の地平から見直す作業が進められている。とりわけ、新たに発見されたセリヌースのテキストなど、聖法や碑文史料の検討が進み、犠牲式の細部についての議論が盛んである。本発表は、犠牲の肉の取り扱いに見る「持ち出し禁止 ou phora」について考察する。「持ち出し禁止」事項は、神々や犠牲の形態を「オリュンピオス/クトニオス」に分類を試みる議論で、「共食」に至らない犠牲式の一つとされた。「クトニオスの」神々への犠牲の肉をすべて焼き尽くしてしまう(ホロカウトス)という習慣が存在したためだ。「持ち出し禁止」を食べられない肉と解釈すれば、それはオリュンピオス的な共食とは相容れない「クトニオスの」祭祀の様子を示すものと考えられた。
しかし、史料中の「持ち出し禁止」事項を見てみると、その事例は多く、「クトニオスの」神格ではない神々への犠牲にも見て取れる。実際、アッティカのデーモスの祭暦では「持ち出し禁止」は、通常の神への犠牲にも頻出する。「持ち出し禁止」は、肉の消費禁止ではなく、消費の場を制限するものではないか。だとすると、「持ち出し禁止」は聖域内での共食を強制し、参加者に聖域の意義をより深く体感させるものではなかったか。このような仮説から、クトニオスの祭祀を陰鬱で拒絶型と解釈する議論を再検討し、神々、犠牲、あるいは祭祀の様態を「オリュンピオス/クトニオス」の類型において説明することの意義を問う。
ローマ帝政初期のウィルギネス・ウェスタレス
遠藤 直子(東北大学)
女性神官団ウィルギネス・ウェスタレスに関する研究は、1980年のMary Beardによる画期的な論考以降今日に至るまで、主に共和政期における処罰・処刑の事例の考察と、祭儀内容や視覚的な表象などからその存在の「曖昧さ」を読み解くという手法が未だ主流であり続けており(とみに後者のアプローチは時代の流れを度外視した共時的な内容となりがちである)、帝政初期におけるウェスタレスの実情に関しては、未だ研究の空白地帯のままである。
帝政の成立という大きな変革の時代において、アウグストゥスは主要な神々を自らの権威に結びつけた。その過程で、ウィルギネス・ウェスタレスは、強調され再認識された共和政以来の伝統の象徴であり、なおかつ皇帝の神聖さの体現者としての役割を期待された ――報告者は先の論文でこのように結論づけた。
本報告では、先の論文で課題として挙げた通り、叙述史料以外の材料をも用いて、帝政初期におけるウィルギネス・ウェスタレスのパーソナル・データを分析し、祭儀のあり方の変遷(伝統的祭儀に加えて皇帝礼拝関連の祭儀も担っていく)と共に彼女たちが時代の中でどのように認識されていたかを考察する。従来、ウェスタレス像はほぼ叙述史料(場合によっては美術や考古学的史料)によって復元されてきたが、碑文史料においては、叙述史料および先行研究が述べてきたこととは異なる状況が示されている。そうしたことを踏まえ、既存の研究における全体イメージとしての「曖昧さ」といった範疇から一歩進んだ、個々の存在としてのウィルギネス・ウェスタレスを把握する一助とした上で、諸史料の相互関係や情報の伝達状況について改めて考える機会としたい。
D.19.2.35.1に見る古代ローマ共有農場の相互賃貸借
――「古典期法学」批判を視野に――
佐々木 健(京都大学)
標記法史料が伝えるのは、共有農場を有する両当事者が隔年で交互に耕作・収穫を行なっていたところ、一方の乱用により翌年の収穫が損なわれた場合における精算問題である。地主・小作関係を含む賃貸借法制の一態様としてこれに注目する「ローマ法学」の観点から蓄積された先行研究は、それにも関わらず「古典期」の姿を描こうとする点で共通する。「インテルポラーティオー狩り」と評された過度の史料批判を過去の遺物として割り引くとしても、引用元として紹介されるアフリカヌス、その『質疑録』の応答者と想定されるユリアヌス、彼らにとっての先達である筈のセルウィウスという三名の法学者に言及されるテクストから、どの部分を誰の見解に帰するべきか、容易には判断がつきにくい。時には、記述内容の「単純性」という評価を根拠に年代測定を試みる学説さえ散見される。
本報告では、一方で古代ローマ私法の断面を紹介しつつ、他方でローマ法学の「闇」としての「古典期法学」概念を批判するための素材として、標記法史料を取り上げる。それは同時に、モムゼンが一身に担っていた法学と史学とが以後には「分裂」した状況を、少なくとも相互対話が可能な姿へと修正する試みでもある。つまり、F・シュルツによる定式に従って、古拙期・ヘレニズム期・古典期・官僚期に「法学」を分かつ理解は、例えば経済史(U・フェルメト)など社会科学的歴史研究とは没交渉に展開されており、ましてや近時の時代区分(不要)論が法制史に反映されることもない。歴史社会学としての「ローマ法(学)」を志向するならば別だが、古代ローマ社会の実相を把握して法の動態的把握を目指す「ローマ法史」にとって健全な理解とは、本報告で取り上げる事例においては如何なるものか。批判と議論によって建設的対話が成立するよう努めたい。
(所属などは発表時のものです。) |